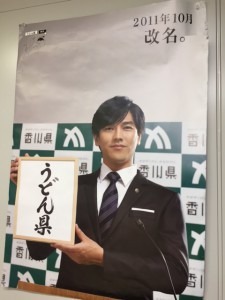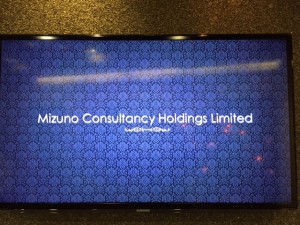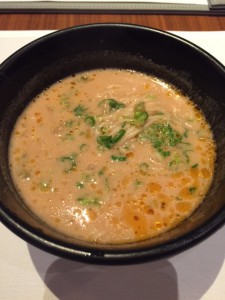昨日の朝に高松から松山に移動。
移動は、大学時代の同級生松本君(高松在住)が運転を買って出てくれた。
松山到着直後に食べた郷土料理。
鯛飯が美味しい。

宿泊したホテルは道後温泉の真ん前。
何とも穏やかな雰囲気だ。



松山訪問の目的は時事通信さん。
以前、上海でお世話になった宗澤さんが、松山支局長をされているので、今回香川出張が入ったのを幸いに、ご挨拶をかねて足を延ばす事に。情報交換など。夜は宗澤支局長自らアテンドを買って出て頂いた。「日本酒党の水野さんは是非ここ!」とお連れ頂いたのは愛媛の地酒アンテナショップ。何種類もの地酒が気軽に飲める夢のような場所だ。

店は立ち飲み。本社勤めの頃も、新橋では立ち飲み屋を専門に攻めていたという宗澤さんに、立ち飲み道を伝授される。大変楽しく、軽く飲んだら食事の店に移動の筈が、夜9時までここで飲んでいた。


二次会は、飛び込みで入ったしぶいもつ焼き屋。
この時点では、3人ともかなり日本酒が入っているので、顔が眠そうだ。

そんなこんなで、愛媛の地酒を8種類ほど試し、地元のディープな雰囲気も楽しめた一夜であった。
今日は午後3時便で東京に移動。
松山空港の寿司屋に入り昼食を取ったが、値段はそこそこ高いが、思った以上に刺身の鮮度がよい。
良い気分で搭乗。また来たい!と思った松山であった。


搭乗前に、空港の書店で坊ちゃんを購入。