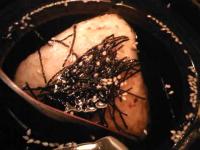|
何故か物悲しい顔に写った写真
|
昨日慕情の後、SEEDで軽く酒を飲んだ。
ふと気が向いて自分の写真を撮たら、妙に物悲しい顔で映っていて驚いた。
気分は全然悲しくなかったのだが。
考えていたのは、会社も3年で軌道に乗ったし、真面目で良く働く部下ばかりだし、クライアントは良い方ばかりだし、自由にやりたい仕事ができるし、幸せだなあ、などと、のんきな事だったのだが。
不思議なものだ。
顔と気分は必ずしも一致していないのか!?
1人のバーは、人をさびしい顔(物思いにふけった顔)にしてしまうのか。
|
シティスーパーで買った日本の卵
|
話変わって、一昨日シティスーパーに行ったら日本の卵が有った。
昨日ジャスコに行ったら、更に、豊富な種類が揃っていた。
今年早々は鳥インフルエンザ。それから原発関係でずっと日本の卵が入手できず困っていた。
そばやチキンラーメンに入れるのは、やはり日本の卵でないと美味しくない。
そんな訳で、日本の卵が変えて大喜びだ。
この数カ月の嬉しいニュースTOP10に入るくらい嬉しい。