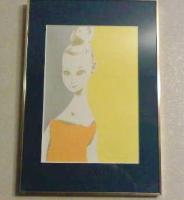クライアント様の質問に対応しつつ、講演会のレジュメ作成に追われるここ数日間。
昨日は、2月7日のチェイスチャイナの講演会のレジュメの作成をやっとの事で終わらせる。
現時点で、今年の上半期で、以下の通り10件の講演会(ジェトロの講演会は、1日2本x2日なので、それを考慮すれば12件)の講演会が決まっているが、まだ増えるはずだ。
講演会は、中国ビジネスをしている方の声を直接聞けるチャンスでもあり、非常に重要な機会。
ご依頼があれば、前向に対応したいと考えている。
<現時点で決まっている講演会>
2月7日(チェイスチャイナ・横浜)、13日(日中投促・東京)、23日(蘇州日本商工会)、3月1、4日(ジェトロ・東京)、7日(商工中金・上海)、5月16日(日経新聞・東京)、21、22(MCH自社主催・香港、広州)、6月20日(みずほ総研・東京)
話変わって、常駐代表処という組織に付いて思う事。
常駐代表処というのは、日本でいうところの駐在員事務所だ。
営業行為ができないので、日本人の感覚では、現地法人より格下という意識が強く、丸紅在籍時代も、常駐代表処から現地法人への格上げ(逆は格下げ)という表現を、当たり前のように使っていた。
現地法人を駐在員事務所に格下げすると、スタッフのモチベーションが下がる懸念がある、と心配する人が多かったし、僕も、丸紅厦門会社を厦門駐在員事務所に組織変更した時(兼任ベースで主管者をしていた)、「社長から所長に格下げになってしまったよ」と感じたものだ。
ただ、何人かの中国人の方の意見を聞くと、中国での受け止め方は、必ずしもそうでないようだ。
というのは、「常駐代表処は本社直結組織だが、現地法人は子会社に過ぎないので、当然、常駐代表処の方が各上というイメージ」と発言する人が多いため。
感性は人それぞれだろうが、こういう考え方もあるのか、とちょっと驚いた。
因みに、中国で常駐代表処を作るのは難しい(難しくなってきている)という噂もあるようだが、どうしてこんな噂が流れたのだろう。
規制業種は常駐代表処を作る事も難しい場合が有るが、これは、現地法人でも同じこと。
メーカーや商社等の常駐代表処開設は問題ないし、僕の会社自身、ここ数か月でも、常駐代表処の開設をお手伝いした実績は何件もある。
ただ、2010年から、規模的な制限はつけられている(外国企業の常駐代表機構の管理の一層の強化に関する通知、工商外企字[2010]4号)。
常駐代表処に駐在する外国人は、代表登記証を元に、居住許可を取得する。
従来は、この人数に制限はなかったが、2010年から4人以内に制限されてしまった。
つまり、駐在員は4人以内とする事が強制された訳だ。
開設地域の立場からすれば、常駐代表処は税金(企業所得税、流通税)が取れない、若しくは、経費課税方式で、少額の税金が取れる程度。
「規模がそこそこ大きくなってきたら、(税収に繋がる)現地法人にしなさい」という実利から来た規制であろう。